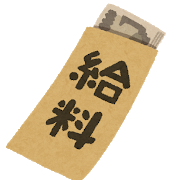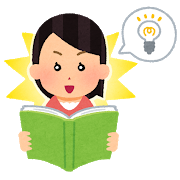
その他資産・負債、営業外損益、特別損益と諸勘定とか雑勘定と言われる科目についてまとめてお話をします。 その他資産・負債の監査は、一般に新人の科目となります。しかし、結構エラーが潜んでいるものです。例えば、人件費に関係する科目がその他資産・負債には存在しますが、特に労働保険については、間違った処理が継続していて、多額のエラーが生じる可能性があります。 労働保険で1年分を3回に分けて支払う場合は、一旦、前払いした分を前払費用などの科目に入れて溜めておき、費用計上の仕訳とは切り離すことが実務上は多いですが、このケースにおいて、前払費用を消す仕訳が漏れるケースが散見されます。ミスのパターンは様々ですが、資産と負債が両建てで膨らんでいる場合は、総資産が膨らむのみで損益にインパクトがないですが、本来費用処理していないといけないのに、前払費用に残ったままになってしまっているとそれなりの損益インパクトのあるエラーが発生します。
また、その他資産・負債に資産性がないのに資産として計上されている科目が存在するということも散見されます。例えば、何らかの理由で長期前払費用として計上したが、その既支払額から得られる効用がなくなる事由が発生しているにも関わらず、いつまでの規則的な償却を行ってしまっているということがこの事例に相当します。そこそこよくあるので注意が必要です。 基本的に、その他資産・負債は、金額が小さいので、手続きをやり過ぎないという注意も必要となります。ある意味やりがいのあるよくわからない科目が存在したりするので、いたずらに無駄に細かく見る人がいますが、金額的な重要性を気にせずに無駄に手厚いバウチングなどを行う会計士は、残念ながらセンスのない会計士といえるでしょう。金額的に少額であるが気になる場合は、まずきっちりとヒアリングをして、エラーが潜んでいる可能性があり、かつこのまま放置するといずれ大きくなる可能性があったり、質的に重要な場合にバウチングをすると良いと思います。
営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失の監査手続きで特に留意することは、まず、チーム全体が把握していない大きな金額の臨時・異常な項目がないことを確認をするということです。ほとんどないのですが、会社から申告をうけていない大きな損失や利益が発生していることがあり、場合によっては、重要性の基準値を超えるような臨時科目が発生していることがあります。このような場合には、まずそのような科目があるということをチームで共有し、その処理が妥当であるかどうかという検討に入ることが重要です。 仮に新人がこのような科目の存在を発見し、チームに報告した場合には、この部分についてのみおそらく担当から外れることになるでしょう。
また、営業外以下の損益項目は、それと関連する貸借対照表項目の担当者が見ることが一般的です。そのため、手続きが重複しないよう、営業外以下の担当者は、関連する貸借対照表項目の担当者とどちらが見るか意思疎通を図る必要があります。例えば、固定資産売却損や減損損失などは、一般に固定資産担当者が見ることになります。投資有価証券の評価損や投資有価証券売却損などは、一般に投資担当者が見ることになります。営業外以下の担当者がどちらが見るかを確認することによって、関連する貸借対照表科目担当者もそのような事象があり、見る必要があるという認識をすることになりますので、このような観点からも意思疎通が重要となります。
近年の会計における理論的な流れからは、特別損益項目は発生しにくくなっており、会社は特別損失としているが、本来は、売上原価又は販売費および一般管理費で計上をする必要があるということが散見されます。この場合、金額的にそれなりに多額となることが多く、注意が必要となります。 また、特別損益項目か営業外損益項目かという視点も必要となります。前述の特別損失が本来営業項目という場合もそうですが、会社はなるべく上の方の段階損益が良くあること求めるため、利益はなるべく上の項目で、損失はなるべく下の項目で計上したがる傾向になります。そのため、段階損益を跨ぐような計上場所のエラーには特に注意が必要となります。
なお、収益と費用をグロスで表示するか、ネットで表示するかという視点も重要です。総額主義の原則があるため、グロスが原則ですが、為替差損益などのようにネットが求められる科目もあります。グロスで表示する場合は、収益が売上に計上され、費用は、営業外費用に計上されるという費用収益が段階損益的に対応していない状況は避ける必要があります。 開示という観点からすると四半期の別掲基準、期末の別掲基準に則り、強制的に開示を要する科目を科目監査の段階で明らかにしておくと、大きな問題が発生しないことになります。なお、雑収入や雑損失という科目は、元帳または仕訳を通査し、必要に応じてヒアリングやバウチングを行い、別掲を要する科目がないか、計上する段階が異なる科目がないかの確認を必ずする必要があります。少額であり当期に修正はしない場合でも引き続き発生する取引で計上区分に誤りがある場合には、会社に伝達をして次回以降は適切な区分に計上するように求めることも必要になります。