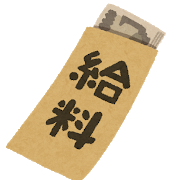有価証券や投資有価証券などの投資科目は、まとめて監査担当科目としての割り振りを行うのが一般的です。一般事業会社であれば、複雑な金融商品があることは少ないと思います。大まかに言うと、金融商品に関する会計基準に則った処理を会社が行っているかを監査することになり、保有目的に応じて、有価証券なのか、投資有価証券なのか、関係会社株式なのかなどを判断し、それぞれの区分に応じた処理がなされているかを監査します。他にも会計基準よりも詳細を定めた金融商品に関する実務指針、金融商品に関するQ&Aなどの会計基準などがあり、これらに則った会計処理がなされていることを確認します。
有価証券の監査において、上場有価証券か非上場有価証券かで、監査手法は大きく異なります。上場有価証券であれば、数量は確認状、単価は時価情報との照合により確認します。非上場有価証券は、数量は確認状で確認し、金額は過年度からの積み重ねで立証し、減損の有無が重要となります。非上場株式の減損の要否については、直近の決算書を入手し、一株当たり純資産金額が帳簿単価を下回っていないことを確認します。なお、減損を行った有価証券の税効果の処理は特殊になっているので注意が必要です(金融商品会計に関するQ&A Q3「過年度にその他有価証券を減損した場合の税効果会計の取扱い」)→削除になったが、この取り扱い自体に変更はないです)。また、株式や債券について減損処理や引当処理をした場合には、評価を戻すかどうかというのも様々なパターン(半期か期末か、洗替法を採用していうか、対象が株式か債権かなど)があることから、どのようなケースで評価を戻し、どのようなケースでは評価を戻さないということをきちんと把握しておく必要がいあります。
例えば、100%子会社については、純資産額をベースにして評価することが一般的ですが、回復可能性がないと認められ減損した場合に戻入れることは認められません。100%子会社に貸付を行っている場合には、債務超過金額見合いについては貸倒引当金を計上する必要がありますが、この引当金については、債務超過が解消した場合には引当金を取り崩すことになります。
投資については、色々な論点があるので以下に簡単で一般的な論点について箇条書きにしてみましょう。
・ ゴルフ会員権は、株式方式か預託金方式かで処理が変わるので注意が必要です。預託金方式の場合には、預託保証金部分を上回る部分については評価損を計上し、預託保証金部分の範囲内については預託保証金に対する貸倒引当金を計上する必要があります。→金融商品会計に関する実務指針145項、311項、金融商品会計に関するQ&A Q46など
・ 一定程度利息を受け取れていない未収利息については、未収利息を取崩し、以降の未収利息を計上してはならないので注意が必要です。→金融商品会計基準(注9)、金融商品会計に関する実務指針119項など
・ 一般債権の評価区分が適切になされているかの確認が必要です。「一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する 」なお、評価区分を変更された場合にはそれが利益操作に該当しないことなどを注意深く確認をする必要がある。→金融商品会計基準28項(1)、金融商品会計に関する実務指針110項など
・ 親子上場しているケースで上場子会社株式は時価ではなく、原則として取得価格で評価する必要がある。→金融商品会計基準17項
・ 親会社株式を長期間保有していると会社法違反となる。原則保有禁止で例外的に認められている場合であっても子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない旨が定められている。また、親会社株式等(親会社株式、その他の関係会社株式など)については期末評価についてQ&Aに定めが記載されており、親会社株式は取得価格、その他の関係会社株式は時価で評価する。なお、ここでは定義が重要になってくる。参考 関連会社は財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(その他の関係会社)をいう。関連会社とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。→会社法第135条、金融商品に関するQ&A Q16、財務諸表等規則第8条5項、8項
・ 流動資産に有価証券として表示する投資資産には、売買目的有価証券だけではなく、満期が1年以内に到来する満期保有目的の債権も含まれるため、満期保有目的の債権の満期は常に意識をして漏らさないようにする必要がある。→金融商品会計基準23項など
・ ヘッジ会計の要件を満たさない投資対象に対してヘッジ会計を適用しないように注意をする必要がある。→金融商品会計基準31項など
・ 金融商品の取得にかかる付随費用が取得価格に含まれているか注意する必要がある。ただし、自己株式の取得にかかる費用は、資本取引損益取引区分の観点より費用で処理されているか注意する必要がある。自己株式取得の付随費用は販管費に計上されがちであるが、財務コストであるため営業外費用に計上されていることを確認する必要がある。なお、単体決算上は子会社株式の取得にかかる付随費用は取得価格に含める必要があるが、連結上は子会社株式の取得価格に付随費用は含めないため、連結財務諸表の作成にあたり個別の修正仕訳が必要となる。→金融商品に関する実務指針56項、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 14項、企業結合に関する会計基準26項、金融商品に関するQ&A Q15ー2など
・ 有価証券の減損処理について、ある程度詳細なルールが定められており、該当する場合には見積りの要素は回復可能性の部分のみであり明らかなエラーとなる可能性がある。→金融商品に関する実務指針91項、92項