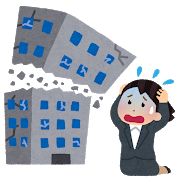上場支援作業において、注意するべきデリバティブ資産・負債を時価評価していないという上場準備会社はよくあります。デリバティブについては、税務と会計が基本的には一致することになりますので、修正が入る場合には税務の申告も直す必要があります。でも、比較的よくある間違いになります。また、以前よく銀行に勧められてお付き合いで会社が取引をしているのを見たのが金利スワップです。特例処理のものが多いのですが、特例処理が適用できないものは、時価評価が必要になるので注意が必要です。海外取引がある企業でよく見かけるのが為替予約です。為替予約は、そもそもヘッジ会計が適用できるのかの判定が一番難しい部分になります。事前の評価、事後の評価、ルールの有無などからヘッジ会計が適用できるかどうかの判定を行いますが、ヘッジ比率が高すぎないか、ヘッジ期間が長すぎないか、ルールを守っているかというような観点から投機ではなくヘッジであると判断できるかどうかという辺りがキモになるかと思います。為替予約は金額が大きくなるケースが多く、ヘッジ会計を適用するのか、時価評価なのかで業績に大きな影響があることから非常に重要な監査論点となるケースが多いです。
近年、海外に製造委託し、日本国内に輸入して日本で販売をするというタイプのビジネスが、海外の格安な人件費や円高により増えていました。ここで、このようなビジネスを行う会社において、為替変動の影響をヘッジする目的で、通貨スワップ、金利スワップ、為替予約等の様々なデリバティブ取引を行うケースが多く発生します。
デリバティブ取引は、原則として税務上も会計上も時価評価をする必要があるのですが、時価評価をせずに簿価で評価してしまっているケースが多発しています。そのため、IPOに当たり、多額の時価評価損失を計上せざるを得ないようなケースが発生します。デリバティブ取引における時価は、金融機関から送付されてきますが、税理士や会計士が、この読み方がわからなかったりするために何となく簿価で計上されてしまっていることもあるのかもしれません。
また、ヘッジの要件を満たさないのに、ヘッジ会計を適用してしまうケースも散見されます。ヘッジ会計の適用を考える場合は、顧問税理士や監査法人に相談をして、ヘッジ会計適用のための要件をしっかり満たす必要があるので、ご注意下さい!
上場支援作業において、注意するべき事項として貸倒引当金の設定が税法ベースになっているということは、IPOを目指す上場準備会社の初期の段階でほぼすべての会社といって良いくらいよくある事項です。上場を考えなければ、税理士としては税務と会計が一致している方が負担がないですから当然といえば当然ですよね。税務と会計では、同じ3期間分を用いて実積率を算定するにしても利用する期間が異なることになります。理論的には会計で利用する期間対応が妥当なように思われます。税務は課税の公平が主眼となるため、会計が目的とする適正な期間損益計算とは理論的に異なる処理を行うことがしばしばあります。
そういえば、税法改正によって、所謂、大会社は一般・個別とも貸倒引当金を損金算入できなくなりますよね。実質的に、法的に貸倒が確定するまでは、損金算入ができないため適切に債権管理をする必要がありますね。このようなケースでは、会計上は実質的な回収可能性の観点から回収不能と見込まれる部分については費用処理されますが、税法上は客観的な事実に基づくまで損金算入できないため、法人税の申告書上で加算し、将来減算一時差異になります。そのため、IPOを目指す会社においては、この部分に税効果会計を適用する必要が出てきます。色々と面倒なのが上場会社の会計なのです。
ところで、貸倒実績率の算定期間において、貸倒実績がないということがたまにありますが、この場合は、無理やり税法ベースで貸倒引当金を計上したり、最も近い貸倒実績を利用したりするケースがありますが、個人的には無理やり貸倒引当金を計上する必要性はないと思います。確かに、金融商品会計実務指針Q&AのQ40においては、算定期間においてゼロだからといって安易にゼロとしてはいけないように記載がありますが、特に過去の最も近い貸倒れを実積率に反映させる方法の場合は、直近がそこそこ昔で金額的に大きな貸倒れが発生した場合に、貸倒実績率を大きく歪めることになります。このような場合を考えると、直近の貸倒を無理やり用いるのは問題とも考えられます。